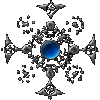
close this window
|
遠くの夜空を染め上げる、色とりどりの光の競演。
その轟く音と、お祭りの喧騒によって、辺りの音がよく聞こえない。 でも、音の聞こえない原因は周囲の騒音じゃないってことは、あたしが一番分かっている。 だってさ… 今一番大きな音は、あたし自身の心臓の鼓動なんだから―― いのち、つながり。 これも全部、今隣にいるこいつのせいだ。 『…今日の花火、一緒に見に行かないか…?』 朝方にそう言われてから、あたしは今日一日ずっとそわそわして落ち着かなかった。 今だってそう。こいつが隣にいるだけで、鼓動が速くなって仕方がない。 あの温泉旅行の夜や、こいつに膝枕をした時に比べたら、まだマシだけどさ…。 こいつに誘ってもらって、あたしは嬉しい? それとも…怖い? どっちなんだろう。両方半々で感じているような気もするし、どちらか片方のような気もする。 ただひとつはっきりしているのは、こんな風に自分の気持ちもよく分からなくなるくらい、今のあたしは緊張しているってことだ。 |
|
§
前にこいつから、隊員のみんなとハイネスの花火大会に行ってきたという話を聞かされたことがある。 『どうだ、綺麗だろう?』 こいつは妙に嬉しそうに、花火の写真をあたしに見せてくれた。 でも、その時のあたしは沸いてくる醜い感情を押さえ込むのに必死で、写真どころではなかった。 ――どうして、あたしを誘ってくれなかったのよ―― いや、これは完全にあたしの身勝手な思いだ。光刃はあたしだけのものじゃないし、【ミスリルを冠する者】として隊員と行動を共にするのは普通のことよね。それに、あの時別行動だったあたしはきっと誘われても行けなかったに違いない。 そうだ、だからあれは仕方のないことだったんだ―― そう自分に言い聞かせるのに必死で、こいつの顔もろくに見ることができずにいた。 あたしはずっと、好きになった相手のことを束縛するような嫌な女になりたくないと思ってきた。でもその綺麗で楽しげな写真を見た時のあたしは、そんな「嫌な女」そのものになってしまっていたんだ。 |
|
§
「ここに座るか。よく見えるぞ、ミキ」 嫌な記憶に飲まれそうになっていたあたしは、こいつの声で現実へと浮かび上がる。 本当にこいつは…。 どうしてこう、助けてほしいときに助けてくれるんだろうね、あんたは。 普段は救いようがないくらい鈍感なのにさ…。 きっと、今のだってこいつは何も考えずに言ったんだろう。 あたしを助けようなんて、いつもいつも考えてるヤツじゃないことは分かってるけどさ。 でも、あたしはこいつの何気ない仕草で何度も救われてきた。それは紛れもない事実なんだ。 「…うん。いいわね、ここにしましょ」 あたしはこいつの左隣に腰を下ろす。でも、なんだか恥ずかしくて距離を空けて座ってみる。 どぉおん… ぱらぱらぱら… ひゅううぅぅ… どおおぉん どおん どん… しばらく光と音の競演を見つめる。 やっぱり、好きな人と一緒に見る花火は綺麗だった。 本当のことを言うと、火薬の臭いは村が襲撃された時のことを思い起こすから好きになれない。あのクリスマスの夜に父さんたちに赦されてからは、これでも少しはマシになったんだけどね…。 |
|
以前は火薬の臭いをかぐと、あるはずのない臭い――生き物が生きたまま焼かれゆくあの絶望的な臭い――が混じっているように感じてしまって、誰にも気づかれぬ場所でひとり嘔吐を繰り返していたから。
そんな心の傷から立ち直ることができたのも、こいつのおかげ。 あたしはね、あんたに助けられてばかりなのよ、光刃。 叶うことなら、あんたの感じてる罪の苦しみをあたしが和らげてあげたい。 ねぇ、光刃。あんたはどうして…独りでもそんなに強くいられるのよ…。 あたしはいつの間にか、光刃との間に空けていた空隙を詰めていた。 眩い光に照らされる光刃の横顔に吸い寄せられるように、あたしは手を伸ばす。 あと少しで触れられるというところで―― 「小娘…」 小さく、呟くような光刃の声が聞こえた。 光刃の目線の先を追うと、そこには娘ちゃんとお父さんが寄り添って立っていた。 お父さんは濃紺の渋い甚平を、娘ちゃんは白と淡いピンクが基調の浴衣を。 どちらも上手に着こなしている二人は、花火の強い光によってひとつの影として一体となっていて…まるで恋人同士のようにも見えた。 娘ちゃんたちも見に来ていたんだねぇ。 あたしも光刃も狐のお面を斜めに引っ掛けているから、娘ちゃんにはあたしたちだとは分からないはず。 それに、今日はそれぞれ個人参加。光刃と二人きりで楽しみたいと思っていたあたしは、娘ちゃんから目を逸らして再び光刃の方に顔を向けた。 |
|
§
「…小娘、あいつ…」 光刃は娘ちゃんの方を見続けていた。 ちょっと…あんたが娘ちゃん萌えなのは分かってるけどさ。今はあたしの方を向きなさいよね。 あたしは光刃の左手に自分の右手を重ねる。鈍いこいつも、これで気づいてくれるはず。 …でも、こいつはそれでも意に介さず、硬い表情のまま娘ちゃんの方を見つめ続けている。 さすがにカチンときたあたしは、我慢できなくなって口を開いた。 「…あんた、さっきから娘ちゃんばっかりじゃない? あたしのことも…」 「お前は気づかないのか? ミキ…」 光刃の残念そうな言葉で、あたしの言葉は遮られる。 気づかない? 気づかないって、一体何を… そう思いながらもう一度娘ちゃんをよく見てみる。すると… お父さんの甚平からわずかに覗くそのかわいらしい頬が、濡れているように見えた。 |
|
§
――娘ちゃんが泣いてる―― こういうイベントは誰よりも楽しそうに過ごす娘ちゃん。 それなのに、お父さんに抱かれて泣いているなんて…。 一体何があったの? 分からない。分からないけど…。 あたしは娘ちゃんの様子に気づいてあげることができなかったんだ。 いつも鈍感だと思っていた光刃は最初に気づいていたのに、ね。 どうしてあたしはこうなんだろう。いつも光刃の事になると周りが見えなくなってしまう…。 こんなあたしは【ミスリルを冠する者】失格かもしれない。 もしそうなら、いつか娘ちゃんたちの傍にもいられなくなるかもしれない。 そのうち光刃とも離ればなれになって、そして―― 「…キ。おい、ミキ。顔が真っ青だぞ。大丈夫か…?」 うつむいているあたしの顔を光刃が覗き込んでくる。 こいつの手の甲に軽く乗せていたあたしの右手は、いつの間にか光刃の左手によってしっかりと握られていた。 心配そうな光刃の目。何故か軽く上気しているようにも見えるこいつの顔だけど、今は哀れみの色の方が強く浮かんでいた。 きっと光刃はあたしが感じていることが薄々分かっているんだろう。分かった上で慰めようとしてくれているのだと、その無愛想な顔から読み取ることができた。 でもその時のあたしは、それを素直に受けることができなかった。 |
|
「…離してっ…」 気づけばあたしは、光刃の手を振りほどいて走り出していた。 黒い泉のように湧いてきて、自分の意志では止められなくなった嫌な想像を振り払おうとするかのように。 娘ちゃんたち親子にも、そして光刃にも顔向けできなくなったあたしは、浴衣の裾が乱れるのにも構わず人気のない方へと走っていた。 これは逃避。分かっているけど、でも。 あたしは自分が赦せなかった。 こんなあたしは、光刃と――好きな人と一緒にいることは赦されない。 お祭りの喧噪から逃げるように、あたしは当てもなく走りつづけた。 |
|
§
はぁ はぁっ はぁ… 息が苦しい。 夜とはいえ、季節は夏。流れる汗で浴衣が張り付いてうまく動けない。 ウィンドウォークやバーサーカースピリッツを使う余裕すらなく、ただひたすらに走りつづけたあたしは、いつの間にか小高い丘の上にたどり着いていた。 ここから見えるものは、花火の遺した煙と満月だけ。 ここで聞こえるものは、かすかな風鳴りの音だけ。 「…娘ちゃん… ごめん…ねぇ…」 そんな静謐な世界に、あたしの声が沁みだしては溶け込んでいく。 足がもつれてきたあたしは、流れる汗すら拭わずにその場にうずくまる。 膝を抱えて、顔を足に押し付けて。目蓋から溢れるものを浴衣に染み込ませていく。 【ミスリルを冠する者】の中で、あたしが一番娘ちゃんのことを気にかけていて、よく見ているんだという自負があった。ミクちゃんも年齢的には近いけど、でも娘ちゃんにとって自分が一番身近な姉貴分なのだと。そのことにあたしは誇りすら感じていた。 でも、あたしは娘ちゃんが泣いていることに気づかなかった。気づけなかった。 きっと家族連れが目立つイベントで、お母さんが恋しくなったりしたのだろう。お父さんにしがみついて泣いている娘ちゃんを目の前にして、あたしは自分の好きな人のことしか考えられなかったのだ。 「…嫌な女だねぇ。まったくさ…」 「…誰のことだ?」 |
|
はっとして振り向く。でも、そこに期待した人はいなかった。
…幻聴まで聞こえるとはね。あたしも相当病んでいるのかねぇ。 あいつが追いかけてきてくれる訳、ないじゃないさ。 あたしはあいつが握り返してくれた手を振りほどいて逃げ出したのよ? きっと今ごろ軽蔑されてるわよ。何を期待してるのよあたしは…。 なんだか余計に悲しくなって、力の抜けたあたしはまたひとりでうずくまる。 風鳴りの音に耳を澄ませてみる。こんなときは耳障りな音もやさしく聞こえるから不思議だ。 さっきまでの熱が引いて、汗で濡れた浴衣が冷えてきている。 今は心地よいけど、着替えないと風邪引くかもねぇ…。 そんなことを考えていると、突然あたしの頭に何かが乗せられた。 「だ、誰よっ!」 やっぱり誰かいる…! あたしは反射的に頭に乗せられたものをはたき落とした。 落ちたものを見てみると、それは娘ちゃんからもらった狐のお面だった。 そう。あいつとお揃いの…。 |
|
§
「…途中に落ちていたぞ。やはりお前のだったか」 「べ、別にお前の為に拾ったわけじゃないぞ。小娘の為だからな。か、勘違いするな…」 ツンデレのテンプレートのような言葉が、あたしのすぐ隣から聞こえてくる。 見上げればそこに、視線を逸らせて赤い頬を掻いている光刃がいた。 “あんた、なんでここにいるのよ” “あたしのことなんて放っておいてよ!” “いつハイドなんて覚えたのよ。全然見えなかったわよ” どれも言葉にならなかった。 こいつに探してもらって、見つけ出してもらって。 あたしはきっと嬉しくて、そしてきっと怖いんだ。 あたしは声も出せずに光刃の顔を見つめる。 声を出してしまったら、それがこの夢のようなできごとの「終わり」の合図になってしまうと思ったから。 「急に走り出すから驚いたぞ。花火も終わったようだし、帰るとするか」 あたしは狐のお面を拾い上げる。いつの間にか落としていたんだねぇ…。 娘ちゃんがあたしと光刃にこれを手渡してくれた時のことが自然と思い出される。 あの時、娘ちゃんは憂いを含んだ顔でこう呟いた。 |
|
――んっとね、ふたりとも正面から向き合うとはずかしくて素直になれないでしょ? だからね――
――狐さんのお面でお顔を隠せば、素直な想いをお互いに伝え合えるんじゃないかなぁって思うの―― そんな娘ちゃんに対して、あたしは軽口を叩いて恥ずかしさを誤魔化すことしかできなかったんだ。 “そんなこと気にしなくても大丈夫よw あたしたちは大人なんだからさぁw” “ああ、そうだぞ小娘。それにミキは狐というより狸がお似合いだろう。体型的にな” “な、なんですって? 馬鹿なこと言ってるとこのドラスレが火を噴くわよっ” …そんな風に軽い気持ちでお面を受け取ったんだ。いつものあたしたちのノリでね。 今思い返すとあたしたちは娘ちゃんにすごく失礼なことをしたと思う。それこそいつぞやの光刃のようにひっぱたかれても仕方ないくらいに。 でも娘ちゃんは怒らず、相変わらず憂いを含んだ顔をしているだけだった。 …本当はあたしも分かってるんだ。娘ちゃんがあたしたちに望んでいることを。 いつになったらそれができるようになるのか、あたしにも分からない。でもそれは時がくれば自然にできるはずだと思う。いつか遠くない未来に、ね。 だから、今はまだ時間がほしくて大事なところで誤魔化してしまうようになった。それが自分の中途半端に実ったこの想いに蓋をすることになってしまっているとしても。 そうやって大事なところでふざけて誤魔化そうとするあたしと、その小さな体で本気であたしたちの母親代わりをしようとしている娘ちゃん。 まったく、どっちが大人でどっちが子どもなんだか…。 本当は誰よりも母親に会いたいと願っているのに、それを押し隠してあたしたちのことを「母親代わり」として真剣に考えてくれている娘ちゃん。到底十四歳の子が持てる覚悟じゃないのに…。 |
|
どこまで背伸びをするつもりなんだろう。いつか折れてしまうのではないかという不吉なイメージが頭を過ぎるけど、今日みたいにお父さんの前で素直に泣けるのなら、きっとこの先も大丈夫だと信じたい。
そんな強くて儚い娘ちゃんを思い浮かべて、あたしはまたひとりで泣きそうになる。 その重荷になっているのが他でもない自分なんだということを再認識してしまったから…。 「…早く帰って着替えないと風邪をひくぞ。これ以上俺を心配させるな」 すぐ近くに光刃はいるはずなのに、その声は少し遠く聞こえた。 娘ちゃんのことを考えすぎていたからだと思う。 でも… 心配って…? 光刃はあたしを心配してくれているの…? どうして? あたしはあんたしか見えてなくて、娘ちゃんが泣いてるのに何のフォローもできなくて。 挙げ句の果てにあたしはその場から逃げ出したのよ? ねぇ、光刃。どうして…あんたはそんなにやさしいのよ… 「…小娘たちはあの後すぐ、元気に走って行ってしまったぞ。 まったく、羨ましいくらい仲のいい親子だよな… ほら、俺たちもそろそろ行くぞ」 光刃はさっきから黙っているあたしの代わりに、無理に会話を探しているようだった。 帰宅を促す為にあたしに背を向けて、でもひとりで立ち去ろうとはせずその場に立ち尽くす光刃。 あたしを待ってくれている… 逃げ出したあたしを赦してくれるの? でも、少なくともあたしと一緒に行こうって思ってくれているんだ…! そう思ったあたしは、もう涙や感情を抑えることなんてできなくて。 言葉にならない声を挙げながら光刃の背中にしがみついていた。 |
|
§
「…こぅ…じ… …光…刃… あたし、自分が赦せなくって…うぅ」 「…何も言うな。俺も深く聞くつもりはない。 きっとお前は、自分の素直な思いと小娘への使命感や忠誠心がせめぎ合って苦しいんだよな」 「うん…うん…」 背中越しに直接伝わってくる光刃の声。 それはいつもより低く、ひどく落ち着いたものに聞こえた。 「俺も【ミスリルを冠する者】だからよく分かる。だがな…」 「人間、ひとりで幾つもの顔を同時には持てん。 使命感に燃える時もあり、自らの思いに素直になる時もある。 さっきのミキは後者だった。それだけのことだろう」 「光刃…」 声を出しても、この時間は終わることなく続いていた。 光刃も消えることなくあたしの傍にいてくれて、あたしの思いを分かってくれている。 それがとても嬉しかった。 月があたしたちをやさしく照らしている。 それと同じくらい、光刃の思いがやさしくあたしに降りそそぐ。 それは本当にあたたかい、光刃にしか出せない「光」だった。 「それにな…」 |
|
そこまで言うと、光刃は少し顔を俯けて続きを言い淀む。
…なによ、そこまで言ったなら最後まで言いなさいよね… あたしは光刃の広い背中に軽くもたれかかりながら、だめ押しの言葉を呟いた。 「それに…?」 「そ、それに… お前が小娘の様子に気づかないほど、俺のことを見ていたということがだな… その、俺はうれ、嬉しかったんだ…。 ミキを独り占めできているんだと思えて、な…」 な… なによ… こんな時にデレないでよね。反則よ… 背中越しに光刃の速い鼓動が聞こえてくる。あぁ、こいつも恥ずかしいんだ。 お互いに顔は見えないけど、真っ赤になりながら必死に本当のことを言ってくれているのが分かる。 本当に…ありがとう。光刃… 不覚にもそんなあんたのこと、かわいいって思っちゃったわよ。 今日のあたしは、くやしいけどあんたに完敗よ。 認めてあげるから…だからお願い。もう少しこのままでいさせて。 あたしの愛しい光刃… |
|
§
「…だ、だから、お前は自分を責める必要はないんだ。 小娘のことはどうせ放っておいても溺愛している父親が何とかするだろうしな。 実際、あの時俺が入り込む余地は残念ながらなかったよ…」 “DOSAN、次は俺と代われ” “リアルフィギュアをお持ち帰りするチャンスが” …光刃が危ないことをブツブツ言っている気がするけど、今は華麗にスルーしてやることにする。 月が高く上って、先ほどより強い光を放っている。 月の光は人を狂わせる力を持つと昔から言われているわよね…。あたしも月の光にあてられたことにして、この秘めた想いを言ってしまいたい。 ――光刃と一緒にいたい。あんたのことが好きよ。愛しているの―― 言うなら今しかない… そう決意したあたしは、光刃の背中に額を押し付けて… 想いを、伝えようとした。 「…光刃、あのさ…」 「どうした? ミキ…」 「あ…あのね、あたしさ… あ、あんたと…」 |
|
「…俺と?」
「あんたと、光刃と、い 一緒にぃ…」 …あぁ、ダメだ。うまく言葉が出てこない… やっぱり怖い…。 ずっと一緒にいたい。それはとても控えめな、あたしの本心の告白。 それすらも言えないなんて…。 あたしの方を振り返った光刃が、あたしをじっと見つめている。 茶化そうとせずあたしの言葉を待ってくれている。 でも、そうやって面と向かって見つめられると余計に言えなくなるのよ…。 あぁもう… どうしよう…。 極度の緊張の中、お面を手渡してくれた時の娘ちゃんの顔がもう一度脳裏を過ぎる。 そうだ。娘ちゃんの本当の望みは…。 ――お面なんかつけなくても、ちゃんと想いを伝えられるようになってね―― ――はずかしいけど、それを乗り越えてちゃんと恋人さんどうしになってね―― それがまだ無理なら、せめて。と、妥協案として狐面を手渡してくれた娘ちゃん。 あの時の憂いのある表情は、本心とは違うことをあたしたちにお願いしているという負い目から来ていたのかもしれない。 …あたしがしっかりしなきゃね。娘ちゃんにこれ以上心配かけられないわよ。 あたしは一旦深呼吸をする為に空を仰ぐ。すると… 妖しげな光を湛えた満月が、厳かに浮かんでいるのが見えた。 |
|
§
魔力すら感じる月を見て、あたしは素直に美しいと思った。 かつて偉大な文豪は月を用いて“あの言葉”を表現した。そんな故事があるけど、これだけ妖艶な輝きを目の当たりにするとその感性もよく分かるような気がする。 今ここで、光刃にあたしの素直な想いを伝えよう。でもそれは、故事になぞらえた形で、できるだけ婉曲的にしよう。 ストレートな言葉は時として互いを傷つける諸刃の剣となってしまう。それを伝えるのは、もう少し関係を深めてからでもいいと思う。 …実った想いを伝えたいけど、もしそれで「伝わってしまったら」。 どちらにしても今のこの関係は終わってしまう。 受け入れられるにしても、拒否されるにしても、ね。 それが今のあたしにはどうしても怖かった。それほどまでに、あたしは今のこの微妙な関係――友人以上、恋人未満の関係――が心地良いと思っているんだ。 だから、今の関係が壊れないように――「伝わらないように」告白すればいい。 光刃には分からないであろうやり方で、真っ正面から。 そうだ。それが誰も傷つかず、あたしも救われる唯一の方法なんだ―― 意を決したあたしは光刃と正面から向き合うと、その目をまっすぐ見つめる。 娘ちゃんの狐面を外して懐にしまい… そして、想いを伝えたんだ。 「…光刃。あたしね、あんたと一緒にいると、月が綺麗に見えるのよ…」 …やっと言えたあたしの本心。きっと光刃には本当の意味は伝わらないだろうけど。 でも、それでいい。それでいいんだ。今はこれがあたしの精一杯なんだから。 ほら、思った通り光刃は同じ姿勢で固まっている。何もリアクションがないところを見ると、「作戦」は成功したみたいね…。 |
|
――本当は伝わってほしかったんじゃないの?―― 心の片隅でそんな声が響く。でもこのやり方はあたしが決めたことなんだ。 自己満足なのは分かってる。光刃もきっとこんなことに付き合わされているとは思ってもいないだろう。あたしは光刃のやさしさを無下にして、自分の想いだけを押し付けるような嫌な女なのかもしれない。でも、それでもあたしにとってさっきの言葉は、紛れもなく愛の告白だったんだ。 しっかり正面から伝えられたわよ、娘ちゃん…。 言ってしまったことで落ち着きを取り戻したあたしは、今更ながらに汗で濡れそぼった自分の体が気になり始めた。 冷えてきたのもあるけど、それ以上に汗のにおいが…。 あんなに密着しておいてもう遅いけど、あたしは光刃と距離を取りたくて少し飛び退く。 そして気恥ずかしさを誤魔化すように、少しおどけて会話を紡ぐ。 「…あははw 告白するとでも思った?w ま、まぁ、確かにそんなシチュだったけど…」 「ミキ」 光刃が真剣な声であたしを呼ぶ。きっと狩りの時でも滅多にないような真剣さで。 月に照らされて、いつもより魅力的に見える光刃。 あたしはまばたきもできずに、その視線に捕らえられて動けなくなる。 心臓の鼓動が痛い。息ができない… そう思い始めたとき、光刃がふっと月を見上げてぼそりと呟いた。 「…奇遇だな。俺も、お前と共に見る月が一番綺麗だと思っていた。ずっと前からな…」 |
|
え…?
あんた、今なんて? 月を見上げている光刃の横顔がカッコいいとか、今はそんなことを考えている場合じゃない。 光刃が言ったのって… もしかしたら…? ううん、それはない。ない…と思う。 だってあの光刃よ?ミケちゃんならともかくこいつがそんな故事を知っているようには見えないし…。 でももし、あたしと同じ意味で言ったのだとしたら。 それって… ずっと前からあたしのことを…? あたしは火を噴きそうなほど熱い顔に両手を当てながら、オーバーヒートしそうなほど ぐるぐると思いを巡らせていた。 |
|
§
「…肌寒くなってきたな。風邪を引かんうちにお前も帰るんだぞ。じゃあなっ」 あたしがぐるぐると考えている間に、光刃はパープルメーンホースを呼び出してそれに跨り、 あっという間に目の前から消え失せていた。 ちょっ まっ… …ねぇ、これなんて放置プレイ? あんた少しは空気とか雰囲気とか読みなさいよね、まったく…。 現れた時と同じく、突然消えてしまった光刃。なんだか狐につままれたような気がしてきた… けど、さっきのが幻な訳がないじゃないさ! あたしは自分にウィンドウォークとバーサーカースピリッツをかけ、イエロウィッシュメーンライオンを呼び出して飛び乗ると、今出せる最高の速さで走り出した。 しばらく走っていると、遠くに行ってしまったと思ったあいつが見えてくる。何だか手加減されているようにも感じたけど、きっと気のせいよね。補助魔法がなければ光刃だってこんなものよ。そうして難なく追いついたあたしは、何も言わずに光刃と並んで走ってみる。 今、こいつはどんな顔をしているんだろう? さっきの「告白」で余裕を取り戻していたあたしは光刃の顔を覗き込もうとするけど、こいつはのらりくらりと顔を背けて見せてくれない。 …あによ。余計に気になるじゃないさ。こうなったら絶対見てやるんだから。 「ちょっと、顔見せなさいよ」 「…今は見せたくない」 「どうしてよ?」 「どうしてもだ」 |
|
ったく、顔を見せないとか娘ちゃんのお母さんじゃないんだからさぁ…w
あんたがやっても誰も萌えないっての。あたし以外はさ… そうよ、きっとそんなあんたのことをかわいいとか思うのはあたしくらいなんだから。感謝しなさいよね? ほんのり上気しているようにも見える光刃の耳の裏側を見ながら、そんなことを考える。 それにしても… 何なのかしらね、このくすぐったいような気持ちは。 おかしな話なんだけど、今はこいつのことがかわいくて仕方がない。 きっとこいつは相変わらず無愛想な顔してるんだろうけどね。 「光刃っ!」 気づけばあたしは叫んでいた。 あたしたちを見ているのは虚空に浮かぶ月だけだという意識が、気を大きくさせたのかもしれない。 「…なんだ?」 「あたし決めた。これからあんたの家に行く!」 「な…? いや、俺はこれから深夜の狩りを…」 「狩りなんて一日くらい休みなさいよ。戦士にも休息は必要でしょ」 「それはそうだが… 俺の家に来て何をするつもりだ?」 「べっつにー? 今はただ、あんたと一緒にいたい気分なのさな! あんたが迷惑なら無理強いしないけどさぁ…」 「べ、別に迷惑では… ま、まったく、女ってヤツは気まぐれだから困る… まぁ、お前がどうしてもというなら、つ…つき合ってやらんこともないが、な…」 |
|
相変わらず光刃は顔を背けているけど、耳がさっきより真っ赤だから意味ないわよ。
さっきのくすぐったいような気持ちがどんどん大きくなってきている。一言で言うなら、ツンデレDE男萌え… いや、光刃萌えかねぇ。 お互いに騎乗していなかったら思わず抱き締めて頬ずりしていたかも。危ないところだったわ。 覚悟しなさいよ、光刃。あんたがそんなにかわいいのが悪いんだからね? 今日はこのままあんたのとこに押し掛けて、シャワーなんかも借りたりして。 そして、いつもは話せないようなことを語り尽くすんだから。 あんた夜行性だし、途中で寝るのも禁止よ。分かったわね? 風を受けて熱が冷めたのか、光刃は背けていた顔を真っ直ぐ前に向けて困ったような怒ったような顔をしている。でもね、まだちょいと頬が赤いから凄みはないわよ。あんたも意外と顔に出るタイプだったんだねぇ。 まったく、体は素直なのに心が素直じゃないんだからw 「…ったく、このツンデレ男がw」 「なんだと? お前こそ絵に描いたようなツンデレだろうが!」 「あんですって? どの口が言ってんのよ! 大体いつもあんたは… あ、ちょっ 待ちなさいよ!」 月は天高く昇っているけれど、あたしたちの夜は始まったばかり。 これから始まるであろう楽しい時間を思い浮かべながら、光刃と並んで夜道を走る。 抜きつ抜かれつ、じゃれあいながら。でも一歩ずつ確実に前へと進んでいく。 その戯れている姿は、さながら二匹の狐のよう。 |
|
あたしは嫌な女になりたくないと思っていた。
でも、今日のあたしは嫌なところばかりだった。 それでもこいつはあたしのことを追いかけてきてくれた。傍にいてくれて、あたしのことを分かってくれたんだ。 それだけで、あたしは確かに光刃と「つながって」いるんだと思えて嬉しくなった。 光刃が何を思ってさっきの言葉を呟いたのか、あたしには分からない。 でもいつかはお互いに本当の想いを偽らずに伝えられる関係になりたい。 今はその為の準備期間。だから、焦らずに目の前の光刃としっかり向き合っていかないとね。 この道を照らすのは月の光。おぼろげだけど、シャリシャリという音がしそうな清らかな光。 あたしと光刃はその見えない粒子を踏みしめながら進んでいく。 この先に待つ未来に向かって―― いのち、つながり。 ―完― |